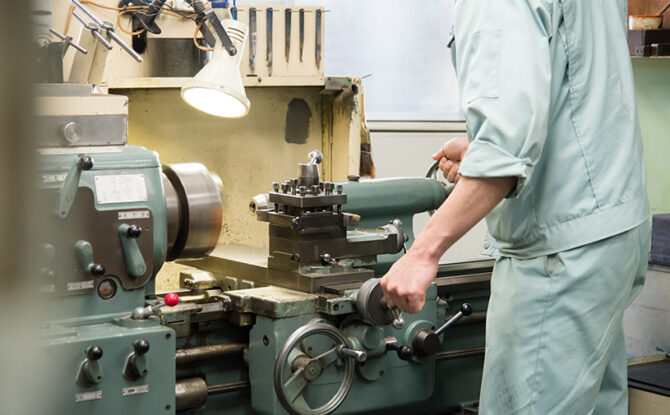
出張中にケガをしてしまったけど、労災の対象になるのか知りたい。
労災の対象になる場合に労災の申請方法を知りたい。
海外出張中でも労災の対象になるのか知りたい。
本記事は、このようなお悩みをお持ちの方のために、書きました。
本記事を執筆した弁護士
目次
1. 出張と労災保険の基本的な関係
出張は、通常の勤務地を離れて遠隔地で業務を行う特殊な勤務形態です。慣れない土地での移動や宿泊が伴うため、予期せぬ事故やケガ、病気に見舞われるリスクも高まります。そのような万が一の事態が発生した際、「これは労災保険の対象になるのだろうか?」と不安に思われる方も少なくないでしょう。
結論から言うと、出張中の災害であっても、業務との関連性が認められれば労災保険給付の対象となる可能性があります。労災保険は、本来、労働者が業務中や通勤中に被った災害に対して、必要な保険給付を行い、労働者の保護を図ることを目的とした国の制度です。
出張は、会社(事業主)の指示に基づいて行われる業務活動であり、その全行程が原則として業務の範囲内にあると考えられます。そのため、出張先への移動中、業務遂行中、宿泊中、あるいは通常の経路での帰宅中などに発生した災害は、労災認定の重要な要素である「業務遂行性」や「業務起因性」が認められやすい傾向にあります。
しかし、全てのケースで労災が認定されるわけではありません。例えば、業務とは全く関係のない私的な行為や、故意による災害などは対象外となる場合があります。どのような状況であれば労災と認められ、どのような手続きが必要になるのか、その判断基準は複雑な場合もあります。
2. 出張中の行為は原則として業務扱い?労災認定の考え方
出張は、通常の勤務とは異なる環境下で行われるため、「どこまでが業務で、どこからが私的な時間なのか」という線引きが曖昧になりがちです。しかし、労災保険の観点からは、出張中の行為は原則として包括的に業務に関連するものとして扱われる傾向にあります。この章では、その基本的な考え方について掘り下げていきます。
2.1 そもそも労災保険とはどのような制度か
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が仕事中(業務上)や通勤中に発生したケガ、病気、障害、あるいは不幸にも死亡した場合に、被災した労働者やその遺族に対して必要な保険給付を行う公的な制度です。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなど、雇用形態に関わらず、原則として労働者を一人でも雇用している事業所に適用されます。
この制度の主な目的は、被災労働者や遺族の生活を保護し、社会復帰を促進することにあります。保険料は全額事業主が負担することになっており、労働者が負担することはありません。
労災保険から給付される主な内容は以下の通りです。
| 給付の種類 | 内容 |
|---|---|
| 療養(補償)給付 | ケガや病気の治療費(診察、薬剤、手術、入院費用など) |
| 休業(補償)給付 | 療養のために働くことができず、賃金を受けられない期間の所得補償 |
| 障害(補償)給付 | ケガや病気が治癒(症状固定)した後、身体に一定の障害が残った場合の年金または一時金 |
| 遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した場合に、その遺族の生活を支えるための年金または一時金 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 労働者が死亡した場合に、葬儀を行うための費用 |
| 傷病(補償)年金 | 療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当する場合の年金 |
| 介護(補償)給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、一定の障害があり、介護を受けている場合の費用 |
出張中の事故であっても、それが業務に関連するものであれば、これらの給付の対象となる可能性があります。
2.2 なぜ出張全体が業務と関連付けられるのか
出張とは、事業主の具体的な命令に基づき、通常の勤務地(事業場)を離れて特定の業務を遂行する活動を指します。これには、目的地への移動、現地での業務遂行、宿泊、そして帰路への移動などが含まれます。
労災認定において、出張が特別な扱いを受けるのは、「労働者が事業主の支配下にある状態」が、自宅を出発してから帰宅するまで継続していると広く解釈されるためです。通常の勤務であれば、事業所内での活動が主となり、業務時間と休憩時間、通勤経路などが比較的明確に区別されます。しかし、出張の場合は、移動中や宿泊先での時間も、業務遂行に必要な付随行為として捉えられることが多いのです。
例えば、出張先への移動中に交通事故に遭った場合や、宿泊先のホテルで転倒してケガをした場合なども、それが業務命令に基づく出張の一環であれば、業務との関連性が認められやすくなります。これは、事業主の命令によって通常の生活圏を離れ、不慣れな環境に身を置くこと自体に、一定のリスクが伴うと考えられているからです。
ただし、「原則として」業務扱いという点には注意が必要です。出張期間中のすべての行為が自動的に労災認定されるわけではありません。明らかに業務から逸脱した私的な行為(例えば、個人的な観光や知人との私的な会食など)の最中に発生した事故や、自身の故意によるケガなどは、業務との関連性が否定され、労災認定されない可能性があります。次の章では、どのようなケースが労災認定されやすく、どのようなケースがされにくいのか、具体的な状況を交えて詳しく解説します。
3. 【ケース別】出張中に労災認定される状況、されない状況
出張中の災害が労災として認定されるかどうかは、具体的な状況によって判断が異なります。ここでは、労災認定の基本的な考え方と、認定されやすいケース・されにくいケースについて、具体的な状況を交えながら詳しく解説します。
3.1 労災認定の重要な2つの判断基準
出張中の災害が労災と認められるためには、労働基準監督署によって主に以下の2つの基準を満たしていると判断される必要があります。
- 業務遂行性:労働者が労働契約に基づき、事業主の支配下にある状態で発生した災害であること。
- 業務起因性:その災害が、業務に内在する危険が現実化したものと認められること(業務と災害との間に相当因果関係があること)。
出張の場合、これらの基準がどのように適用されるのか、具体的に見ていきましょう。
3.1.1 業務遂行性 出張における考え方
業務遂行性は、労働者が事業主の管理下で業務に従事している状態を指します。通常の勤務時間内や事業場内での業務はもちろんですが、出張の場合はその範囲が広く解釈される傾向にあります。
出張は、自宅を出てから出張業務を終えて自宅に帰着するまでの一連の過程全体が、原則として事業主の支配下にある状態とみなされます。これは、出張が事業主の命令に基づいて行われるものであり、移動や宿泊、食事といった付随的な行為も業務遂行に不可欠な要素と考えられるためです。
したがって、出張先への移動中、業務遂行中はもちろん、宿泊施設での滞在中や業務に関連する食事中なども、原則として業務遂行性が認められる可能性が高いといえます。
3.1.2 業務起因性 出張における考え方
業務起因性は、災害の原因が業務にあるかどうか、つまり業務と災害の間に合理的な因果関係があるかを判断する基準です。
出張においては、以下のような状況が業務起因性の判断に影響します。
- 移動に伴う危険:公共交通機関の事故、交通事故など、移動には常に一定のリスクが伴います。出張のための移動中に発生した事故は、業務に内在する危険が現実化したものとして業務起因性が認められやすいです。
- 不慣れな環境での危険:出張先の地理や施設、設備に不慣れなことが原因で発生する事故(例:階段での転倒、不慣れな機械の操作ミス)も、業務との関連性が考慮されます。
- 業務内容に伴う危険:出張先での具体的な業務(例:高所作業、重量物の運搬、化学物質の取り扱い)に特有の危険が原因で発生した災害は、業務起因性が認められます。
- 宿泊に伴う危険:宿泊施設の設備不良(例:漏電、火災)や、業務に関連する活動中の事故(例:業務準備中の転倒)などが考えられます。
ただし、労働者の私的な行為や恣意的な行為、業務とは全く関係のない個人的な事情による災害については、業務起因性が否定されることになります。
3.2 出張中に労災認定されやすい具体的なケース
上記の判断基準を踏まえ、出張中に労災認定されやすい具体的なケースを見ていきましょう。
3.2.1 出張先への移動中や通常の経路での帰宅中の事故
自宅から出張先へ向かう途中の事故、出張先から次の目的地への移動中の事故、出張業務を終えて自宅へ帰る途中の事故は、原則として労災認定の対象となります。これは、出張命令に基づいた合理的な経路・方法での移動が業務遂行の一部とみなされるためです。
- 新幹線、飛行機、バス、タクシーなどの公共交通機関を利用中の事故
- 会社が手配したレンタカーや社用車を運転中の交通事故
- 事前に会社から許可を得て自家用車で移動中の交通事故(合理的な経路を逸脱していない場合)
- 駅構内や空港内での転倒事故
ただし、移動中に業務とは関係のない私的な目的で合理的な経路を逸脱・中断した場合、その逸脱・中断中およびその後の移動中の事故は、原則として労災認定されません。
3.2.2 出張先での業務を行っている最中のケガ
これは最も典型的な労災認定ケースです。出張先での会議、商談、打ち合わせ、現場視察、設営作業、研修受講など、本来の業務を行っている最中に発生したケガや病気は、業務遂行性・業務起因性ともに認められやすく、労災認定の対象となります。
- 会議室で資料を運んでいる最中に転倒して負傷した場合
- 出張先の工場で機械操作中に誤って手を負傷した場合
- 建設現場の視察中に足場から転落した場合
- 研修会場で長時間不自然な姿勢でいたことによる腰痛の発症(業務との因果関係が明確な場合)
3.2.3 出張中の宿泊施設内での事故(業務との関連性による)
出張中の宿泊は業務に付随する行為であり、宿泊施設も事業主の支配が及ぶ範囲と考えられるため、宿泊施設内での事故であっても、業務との関連性が認められれば労災認定される可能性があります。
- ホテルの部屋で翌日の業務準備中に椅子から転落して負傷した場合
- ホテルの設備不良(例:風呂場の床が異常に滑りやすかった、天井の一部が落下してきた)によるケガ
- ホテルで発生した火災や地震などの災害による負傷
- 業務に必要な生理的行為(睡眠、入浴、排泄など)に伴う事故(例:深夜にトイレに行こうとして暗闇で転倒)
ただし、宿泊施設内であっても、明らかに業務と関係のない私的な行為(例:過度な飲酒による転倒、個人的な運動器具の使用中の事故)が原因の場合は、労災認定されにくくなります。
3.2.4 業務に関連する出張中の食事中の事故
出張中の食事も、業務遂行に必要な行為とみなされる場合があります。業務時間内や業務に密接に関連する状況での食事中に発生した事故は、労災認定される可能性があります。
- 出張先での取引先との会食中に、提供された食事による食中毒
- 昼食時間中に、業務場所近くの食堂へ行く途中の転倒事故
- 業務時間内に、会社が手配した弁当を食べていた際の異物混入によるケガ
一方で、業務とは関係のない個人的な会食による事故は、労災認定の対象外となる可能性が高いです。
3.3 出張中に労災認定されにくい具体的なケース
出張中であっても、すべての事故が労災認定されるわけではありません。以下のようなケースでは、労災認定が難しくなります。
3.3.1 業務を逸脱した私的行為や意図的な行為によるケガ
事業主の指揮命令下から外れた、労働者自身の個人的な判断で行われた行為(私的行為)や、故意に危険を招くような行為(恣意的行為)が原因で発生した災害は、業務遂行性や業務起因性が否定され、労災認定されません。
- 業務時間中に、上司に無断で個人的な買い物や用事を済ませるために外出し、その途中で事故に遭った場合
- 宿泊先のホテルで、禁止されているにも関わらずベランダから隣の部屋に移ろうとして転落した場合
- 過度な飲酒により酩酊し、階段を踏み外して転倒した場合
- 自己の故意による自傷行為
3.3.2 観光など自由時間中の事故
出張期間中には、業務終了後や休日などの自由時間が存在することがあります。その自由時間を利用して行われた観光やレジャー、私的な知人との面会など、明らかに業務とは関係のない活動中の事故は、原則として労災認定の対象外です。
- 業務終了後に、現地の観光名所を訪れている最中に転倒した場合
- 休日に、レンタカーを借りてドライブ中に事故を起こした場合
- 現地の友人と食事や飲酒を楽しんでいる最中の事故
3.3.3 個人的な恨みによる第三者からの加害行為
業務とは全く関係のない、個人的な怨恨やトラブルが原因で第三者から暴行などの加害行為を受けた場合は、業務起因性が認められず、労災認定されません。
- 個人的な金銭トラブルを抱える相手から、出張先で待ち伏せされて暴行を受けた場合
- 恋愛関係のもつれから、第三者に襲われた場合
ただし、職務上のトラブルが原因で恨みを買い、その結果として加害行為を受けた場合など、業務との関連性が認められるケースでは、業務起因性が肯定され、労災認定される可能性があります。
4. 裁判例の紹介
出張中の労災認定については、具体的な状況によって判断が分かれることが多く、過去の裁判例が重要な参考になります。ここでは、労災認定の判断基準である「業務遂行性」と「業務起因性」がどのように評価されたのか、いくつかの代表的な裁判例を見ていきましょう。
大分放送事件(福岡高判平成 5 年 4 月 28日)
宿泊を伴う出張中に飲酒して宿泊先の旅館の階段から転落して死亡したという事案です。
裁判所は、「本件事故については、 それが宿泊を伴う業務遂行に随伴ないし関連して発生したものであることが肯認されるところ、 業務起因性を否定するに足る事実関係は存しないもので、 利光の死亡は、 労災法上の業務上の事由による死亡にあたるというべき」として業務遂行性及び業務起因性を認めました。
鳴門労基署長事件(徳島地判平成14 年 1 月25日)
海外出張中の労働者が宿泊先のホテルで強盗殺害されたという事案です。
裁判所は、「『業務上』の事由による災害と認められるためには、労働者が労働契約に基づく使用者の従属関係にある場合において(業務遂行性)、業務を原因として生じた災害であり、 しかも業務に内在する危険性が現実化したものと経験則上認められる場合(業務起因性)であることが必要であるところ、 業務遂行中に生じた災害は、 特段の事情がない限り、 業務に起因するものと事実上推定される。」
「出張中の宿泊先で発生したものであるが、 ・・・Aは所定の宿泊施設内で行動していたのであり、 積極的な私的行為や恣意的行為に及んだとは認められないから、 業務遂行性が認められることは明らかである。」
「本件当時、 フラマホテル等において、日本人が強盗殺人等の被害に遭う危険性はあったというべきであり、本件事件は、業務に内在する危険性が現実化したものと解される。したがって、Aの死亡には業務起因性を否定すべき特段の事情はな」いとして、業務起因性を認めました。
5. 出張先で労災事故が発生した場合の手続きの流れ
万が一、出張先で業務に関連するケガや病気が発生した場合、労災保険の給付を受けるためには適切な手続きを踏む必要があります。ここでは、事故発生から労災申請、そして万が一会社が非協力的な場合の対応まで、具体的な流れを解説します。
5.1 事故発生時にまず行うべきこと 会社への報告と医療機関の受診
出張先で労災事故に遭ってしまった場合、パニックにならず、以下の手順で落ち着いて対応することが重要です。
- 安全の確保と応急処置: まずはご自身の安全を確保し、必要であれば周囲に助けを求め、可能な範囲で応急処置を行ってください。状況によっては救急車の手配も必要になります。
- 会社への速やかな報告: 事故の状況(いつ、どこで、何をしていて、どのようなケガをしたか)、ケガの程度などを、できる限り速やかに会社の上司や担当部署に報告してください。電話での報告に加え、後で確認できるようメールなど記録に残る形でも連絡しておくとよいでしょう。正確な報告は、後の労災申請手続きをスムーズに進める上で不可欠です。
- 医療機関の受診: 医師の診察を受け、適切な治療を開始してください。この際、医療機関の窓口で「労災保険を使いたい」と明確に伝え、健康保険証は提示しないようにしましょう。労災事故の治療に健康保険を使用することはできません。
- 労災指定医療機関を受診する場合: 「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を提出すれば、原則として治療費などの窓口負担なしで治療を受けられます。書類は後日提出でも構いませんが、早めに準備しましょう。
- 労災指定医療機関以外を受診する場合: やむを得ず指定外の医療機関を受診した場合は、一旦治療費を全額自己負担し、後日「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」に必要な書類(領収書や診療明細書など)を添えて労働基準監督署に提出し、費用の還付を受けます。
出張先でどの医療機関にかかればよいか不明な場合は、会社の担当者や、厚生労働省のウェブサイトなどで労災指定医療機関を確認しましょう。
5.2 労災申請に必要な主な書類と入手方法
労災保険の給付を受けるためには、被災した労働者自身(または遺族)が、給付の種類に応じた請求書を作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。主な給付の種類と、その請求に必要な様式は以下の通りです。
| 給付の種類 | 主な請求書様式 | 簡単な説明 |
|---|---|---|
| 療養(補償)給付 | 様式第5号(労災指定医療機関等を受診する場合) 様式第7号(労災指定医療機関等以外を受診し費用を立て替えた場合) |
診察、薬剤、処置、手術、入院などの治療費に関する給付です。 |
| 休業(補償)給付 | 様式第8号(休業(補償)給付支給請求書) | 労災によるケガや病気の療養のために働くことができず、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合に、4日目から支給される所得補償です。 |
| 障害(補償)給付 | 様式第10号(障害(補償)給付支給請求書) | ケガや病気が治癒(症状固定)した後、身体に一定の障害が残った場合に、その障害等級に応じて年金または一時金として支給されます。 |
| 遺族(補償)給付 | 様式第12号(遺族(補償)年金支給請求書 または 遺族(補償)一時金支給請求書) | 労働者が労災により死亡した場合に、その労働者の収入によって生計を維持されていた遺族に対して、年金または一時金として支給されます。 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 様式第16号(葬祭料(葬祭給付)請求書) | 労働者が労災により死亡した場合に、葬儀を行った者(通常は遺族)に対して支給されます。 |
これらの請求書(様式)は、お近くの労働基準監督署の窓口で受け取るか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることができます。請求する給付の種類によって、医師の診断書、レントゲン写真、治療費の領収書、賃金台帳の写し、死亡診断書など、添付が必要な書類が異なりますので、事前に確認し準備を進めましょう。
5.3 労働基準監督署への労災申請のステップ
労災保険の給付請求は、原則として被災した労働者本人またはその遺族が行います。会社が代行してくれる場合もありますが、基本的な流れを理解しておきましょう。
- 必要書類の準備・作成: 上記の表を参考に、必要な請求書を入手し、必要事項を記入します。医師に記入してもらう欄(診断書など)がある場合は、医療機関に依頼します。
- 事業主の証明(可能な場合): 請求書には、原則として事業主(会社)による事故発生状況や賃金に関する証明の記入欄があります。会社に依頼し、証明印をもらいましょう。(会社が協力しない場合の対応は後述します)
- 労働基準監督署への提出: 完成した請求書と添付書類を、原則として、被災労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。出張先の事故であっても、提出先は本社や支店など、ご自身が所属する事業場の管轄労基署となります。郵送での提出も可能です。
- 労働基準監督署による調査: 提出された書類に基づき、労働基準監督署が労災認定のための調査を行います。事故の状況や業務との関連性について、会社や医療機関への照会、場合によっては被災労働者本人への聞き取り調査などが行われます。
- 支給・不支給の決定: 調査の結果、労災と認定されれば給付が決定し、指定した口座への振り込みなどが行われます。認定されなかった場合は、不支給決定通知が送付されます。
なお、労災保険の給付請求には時効があり、権利が発生した日の翌日から起算して、療養(補償)給付や休業(補償)給付は2年、障害(補償)給付や遺族(補償)給付は5年で請求権が消滅します。事故が発生したら、できるだけ速やかに手続きを進めることが重要です。
5.4 会社が労災申請に非協力的な場合の対応策
労災保険の申請は、労働者に認められた正当な権利であり、会社の承認や許可がなくても行うことができます。しかし、中には「労災を使わせたくない」「手続きに協力してくれない」といった会社も残念ながら存在します。そのような場合の対応策を知っておきましょう。
- 事業主証明がなくても申請は可能: 会社が請求書の事業主証明欄への記入や押印を拒否した場合でも、申請を諦める必要はありません。証明欄は空欄のまま、会社が協力してくれない旨とその理由を記した書面(理由書など)を添えて、労働基準監督署に提出することができます。労働基準監督署は、会社の証明がなくても、事実関係を調査した上で労災認定の判断を行います。
- 労働基準監督署に相談する: 会社が手続きに協力してくれない、申請を妨害するなどの行為がある場合は、管轄の労働基準監督署に直接相談しましょう。労基署は会社に対して必要な調査や指導を行う権限を持っています。
- 弁護士などの専門家に相談する: ご自身での手続きに不安がある場合や、会社との関係が悪化しそうな場合などは、労働問題に詳しい弁護士に相談することも有効な手段です。複雑な申請手続きの代行や、会社との交渉などを依頼できます。
会社が労災事故の発生を隠蔽しようとする「労災隠し」は、労働安全衛生法違反の犯罪であり、罰則の対象となります。労働者は不利益を恐れることなく、正当な権利として労災申請を行うべきです。
6. 労災認定されなかった場合の不服申し立て手続き
出張中のケガや病気について労災申請を行ったものの、残念ながら労働基準監督署長から労災と認められない(不支給決定)という処分が下されるケースもあります。しかし、その決定に納得がいかない場合、諦める必要はありません。労災保険制度には、決定に不服がある場合に申し立てを行うための手続きが用意されています。
ここでは、労災の不支給決定などに対する不服申し立ての3つのステップ、すなわち「審査請求」「再審査請求」「行政訴訟」について、それぞれの内容と手続きのポイントを解説します。
6.1 審査請求とは 労働者災害補償保険審査官への申し立て
労働基準監督署長の決定に不服がある場合に、最初に行うことができるのが「審査請求」です。
審査請求は、不支給決定などの処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として審査請求を行うことができなくなりますので、期限には十分注意が必要です。
手続きは、「審査請求書」という書面を、処分を行った労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官宛てに提出することで行います。審査請求書には、請求人の氏名や住所、処分の内容、請求の趣旨や理由などを記載します。
労働者災害補償保険審査官は、提出された書類や必要に応じて行う調査に基づき、改めて労災認定の可否を審査し、決定(認容、棄却、却下)を下します。
6.2 再審査請求とは 労働保険審査会への申し立て
審査請求の結果(決定)にも納得がいかない場合、次のステップとして「再審査請求」を行うことができます。 再審査請求は、厚生労働省内に設置されている「労働保険審査会」に対して行います。
再審査請求ができるのは、主に以下の2つのケースです。
- 労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合
- 審査請求を行ってから3ヶ月を経過しても審査官の決定がない場合
再審査請求は、審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行わなければなりません。また、審査請求から3ヶ月経っても決定がない場合は、その3ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内となります。こちらも期限が厳格に定められています。
手続きは、「再審査請求書」を労働保険審査会宛てに提出します。再審査請求書には、審査請求と同様に、請求人の情報、審査請求の決定内容、再審査請求の趣旨や理由などを記載します。
労働保険審査会は、公開の場で審理を行い、裁決(認容、棄却、却下)を下します。この裁決は、行政機関による最終的な判断と位置づけられています。
6.3 最終手段としての行政訴訟(取消訴訟)
労働保険審査会の裁決にも不服がある場合、最終的な救済手段として、裁判所に「行政訴訟(取消訴訟)」を提起することができます。 これは、国を相手取り、労働基準監督署長の行った原処分(不支給決定など)または労働保険審査会の裁決の取り消しを求める訴訟です。
訴訟を提起できる期間は、原則として、労働保険審査会の裁決があったことを知った日から6ヶ月以内と定められています。
行政訴訟は、法律に基づいた厳格な手続きであり、法的な主張や証拠の提出が求められます。そのため、行政訴訟を検討する場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、事案の見通しや訴訟手続き、費用などについて具体的なアドバイスを提供してくれます。
以下に、不服申し立てのステップと期限をまとめます。
| 手続き段階 | 申し立て先 | 申し立て期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 審査請求 | 労働者災害補償保険審査官(都道府県労働局) | 原処分を知った日の翌日から3ヶ月以内 | 最初の不服申し立て |
| 再審査請求 | 労働保険審査会(厚生労働省) | 審査請求の決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内 (または審査請求から3ヶ月経過しても決定がない場合) |
審査請求決定に不服がある場合など |
| 行政訴訟(取消訴訟) | 裁判所 | 原則として裁決があったことを知った日から6ヶ月以内 | 最終的な司法判断 |
労災の不支給決定を受けたとしても、すぐに諦めずに、これらの不服申し立て制度の活用を検討しましょう。ただし、各手続きには厳格な期限が定められているため、迅速な対応が求められます。
7. 注意点 海外出張における労災保険の適用
近年、企業のグローバル化に伴い、海外へ出張する機会も増えています。国内出張と同様に、海外出張中にも業務に関連する事故やケガが発生するリスクは存在します。しかし、労災保険の適用に関しては、海外出張特有の注意点があります。ここでは、海外出張における労災保険の基本的な考え方と、万が一に備えるための制度について解説します。
7.1 原則 日本国内の労災保険は適用外
日本の労働者災害補償保険法(労災保険法)は、原則として日本国内の事業にのみ適用される「属地主義」をとっています。これは、法律の効力が及ぶ範囲が原則としてその国の領域内に限られるという考え方に基づきます。
そのため、海外の支店や工場、建設現場など、完全に日本国外にある事業場で働く労働者(現地採用の従業員など)や、日本の企業から海外の事業へ籍を移して「出向」するような場合には、原則として日本の労災保険は適用されません。これらのケースでは、現地の労働災害補償制度の適用を検討することになります。
7.2 海外派遣者のための労災保険特別加入制度
前述の通り、日本の労災保険は原則国内の事業に適用されますが、海外への「出張」と「派遣(出向など)」では扱いが異なります。
まず重要な点として、日本国内の事業場に所属し、その事業主の指揮命令を受けて一時的に海外で業務を行う「海外出張」の場合は、国内出張と同様に、日本の労災保険の適用対象となります。出張先への移動中、業務遂行中、宿泊先での業務関連事故などが補償の範囲に含まれる可能性があります。
一方で、海外の支店や子会社、関連企業などに「派遣」され、現地の事業場の指揮命令下で長期間働くような場合は、原則として日本の労災保険の適用対象外となります。しかし、このような海外派遣者についても、日本の労災保険による補償を受けられるように設けられているのが「特別加入制度」です。
この制度を利用することで、海外で働く労働者も、日本国内の労働者と同様の労災保険給付を受けることが可能になります。特に、派遣先の国の労働災害補償制度が十分でない場合や、手続きが煩雑な場合に有効な制度です。
7.2.1 特別加入制度の概要
海外派遣者のための労災保険特別加入制度について、詳細は、厚労省が発行している「特別加入制度のしおり」をご参照ください。
8. まとめ
出張中の事故は、移動、業務遂行中、関連する宿泊や食事など、業務との関連性を示す「業務遂行性」と「業務起因性」が認められれば、労災保険の対象となる可能性が高いです。ただし、観光などの私的行為中の事故は原則として対象外となります。万が一事故が発生した際は、速やかに会社へ報告し医療機関を受診、その後、労働基準監督署へ必要な書類を提出して労災申請を行います。手続きや認定に不安がある場合、弁護士などの専門家への相談も有効な手段です。
本記事を執筆した弁護士
無料相談の方法
メールやLINEで無料相談
事務所にお越しいただくことなく、メールやLINEで無料相談が可能です。
メールやLINEでの無料相談を希望される方は、メール相談、LINE(いずれも24時間受付)から、自由にご相談内容を送ってください。
電話、Zoom、事務所での面談による無料相談
電話、Zoom、事務所での面談による無料相談を希望される方は、
お電話(054-689-7792)(平日の9時~17時30分受付)
予約ページ(24時間受付)
LINE(24時間受付)から予約をお願い致します。
予約ページ、LINEからご予約いただいた場合には、日程調整のご連絡をさせていただきます。
よくある質問
Q相談可能な曜日、時間を教えてください。
事務所での面談、電話、Zoomの場合は、平日の10時~17時半です。お昼の時間帯も可能です。相談時間は30分~1時間程度です。
LINE、問い合わせフォーム(メール)でのご相談は24時間受付です。ただし、お返事には御時間をいただきますのでご了承ください。
Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり電話をしたりすることが難しいので、メールやLINEで相談や打ち合わせをすることはできますか?
メールやLINEでの相談も可能ですし、ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。
なお、裁判をせずに示談交渉で解決する場合、ほとんどのケースで、依頼後に事務所での打ち合わせをすることなく終了しています。
Q家族が労災事故に遭ったのですが、他の家族が代わりに相談することはできますか?
はい。ご家族の方が代わりにご相談していただくことは可能です。お子様を連れて事務所にお越しいただいても構いません。
Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
Qどの段階から費用が発生しますか?
相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。
Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。
Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。





